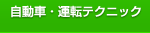2016年6月2日 00:00
スマートIC推進で利便性アップ
国土交通省は、2016年5月27日(金)、都市内交通状況の改善などの効果が期待されるスマートインターチェンジ(スマートIC)に、7カ所を新規事業化すると発表した。また、新たに5カ所で準備段階調査を実施する。スマートICとは?
スマートICとは、ETC専用の小規模なインターチェンジのこと。また、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェンジのこと。主に、サービスエリアやパーキングエリアでの乗り降りができると認識されている。設置が簡単であり、料金を徴収する人員が不要、またすでにある施設を利用するため、従来のインターチェンジと比べて導入費用を抑えられるのがメリットである。
新規事業化される7カ所
次の7カ所が、新たに検討されている箇所になる。なお、スマートインターチェンジの名称は、仮称であり、正式な名称は、地元や利用者お意見を踏まえて決定される。都賀西方(東北自動車道・栃木IC〜鹿沼IC、栃木県)、矢板北(東北道・矢板IC〜西那須野塩原IC、栃木県)、上市(北陸自動車道・立山IC〜滑川IC、富山県)、富士吉田南(東富士五湖道路・富士吉田IC〜山中湖IC、山梨県)、座光寺(中央自動車道・松川IC〜飯田IC、長野県)、足柄(東名高速道路・大井松田IC〜御殿場IC、静岡県町)、駒門(東名高速・御殿場IC〜裾野IC、静岡県)。
中央自動車道の座光寺スマートIC(仮称)は、「SA・PA接続型」として整備される計画となっている。国土交通省によると、このスマートICが整備されると、一般道の渋滞を回避して、高速道路へアクセスが可能になり、市が推進している高航空宇宙産業などにおいて、物流の効率化が可能となる。
例として、周辺企業から名古屋方面(飯田IC)へのアクセス性が向上し、現在の21分から約11分に、10分の短縮になるとしている。
準備段階調査の5箇所
準備段階調査とは、地方で計画検討・調整段階のスマートICにおいて、国として必要性が確認できる箇所について、国がその調査を実施する。これにより、スマートICが地方での計画的、効率的に準備・検討され推進されることが期待されている。新たに準備段階調査を実施するスマートICは、菅生(東北道・村田IC〜仙台南IC、宮城県)、つくば(圏央道・常総IC〜つくば中央IC、茨城県)、甘楽PA(上信越自動車道・吉井IC〜富岡IC、群馬県)、出流原PA(北関東自動車道・足利IC〜佐野田沼IC、栃木県)、東温(松山自動車道・川内IC〜松山IC、愛媛県)の5カ所。
(画像はプレスリリースより)
国土交通省 ニュースリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000690.html
国土交通省 報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/common/001132972.pdf
-->